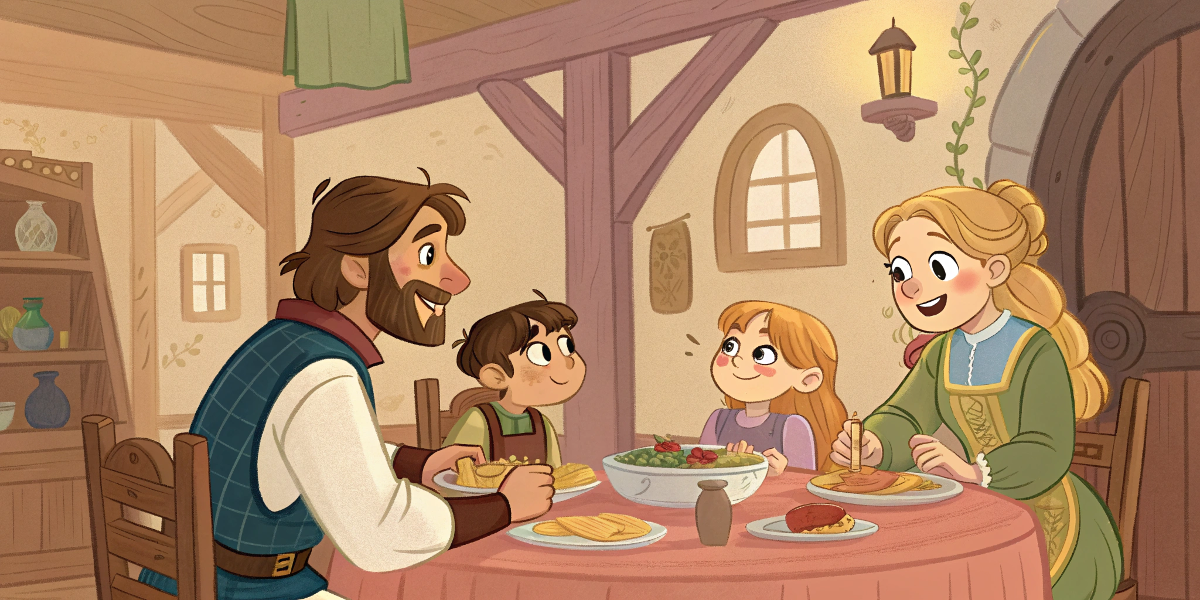はじめに
「再婚した相手の家族との関係が、どこかしっくりこない…」
「パートナーが元の家族を大切にしているけれど、正直よくわからない…」
再婚後の家族関係は、単純なものではありません。特に、「血の繋がりはないけれど家族」と考える人と、「血縁があるからこそ家族」と考える人の間では、価値観のズレが生じやすいものです。
この記事では、「血縁と家族のつながり」「再婚家庭の家族関係」「家族の役割の違い」について、実体験とデータを交えて考えます。
再婚をした人や検討中の人、家族の価値観の違いに悩む人にとって、具体的な考え方のヒントになれば幸いです。
この記事で述べる考え方は、あくまで私個人のものです。「私の意見が正しい!」と主張するものではなく、皆さんが持つ価値観を大切にしていただければと思います。
また、家族関係に悩んだとき、専門家のアドバイスを受けることも一つの方法です。以下のカウンセリングサービス【Kimochi】では、公認心理師のみがカウンセリングを担当する、安心・信頼のサービスです。再婚家庭の相談も可能ですので、ご利用を検討されてみてはいかがでしょうか。
再婚後の家族関係は難しい?『血縁』と『家族の定義』
「家族とは何か?」
これは再婚後の家族関係において、多くの人が直面する問題です。
特に「血縁があるからこそ家族なのか、それとも血縁がなくても家族として成り立つのか?」という点で、考え方が分かれます。
1. 「血縁があるから家族」
日本では「血のつながり」を重視する文化が根強くあります。
- 戸籍制度や遺伝的なつながり を意識する場面が多い。
- 「実の親子・兄弟だからこそ助け合うべき」 という考えが一般的。
- 親族間の扶養義務 など、法的にも血縁を基盤とした制度が多い。
2. 「心の繋がりや一緒に築いた絆で結ばれる家族」
血のつながりがなくても、家族として強い絆を築くことは可能です。
- 一緒に過ごした時間や経験が家族の絆を深める。
- 継父・継母、義理の兄弟姉妹、養子など、血縁のない家族関係でも強い結びつきを持つケースがある。
- 「お互いが家族として認識し、尊重し合うこと」が本質的な家族の条件。
私自身も、明確に「関係性で家族が決まる」 と考えています。
プロフィールにも記載していますが、私の家族には実父・実母・継父・継母・異父妹・フィリピン人の妹2人 がいます。
血のつながりがない関係も多いですが、私は彼らを家族として大切に思っています。
継母は私を「アナク(息子)」として知人や友人に紹介してくれますし、フィリピン人の妹たちも「クーヤ(お兄ちゃん)」と呼んでくれます。妹の学校行事に兄として参加したこともありました。
これは単なる呼称ではなく、彼女たちが私を家族として受け入れてくれている証 だと感じています。
しかし、こうした考え方は日本で決して多くはないでしょう。
実際、「養子縁組意識調査」のデータを見ても、人によって家族の定義が異なることが分かります。
以下は令和3年、公益社団法人商事法務研究会による
“未成年期(20歳に達するまでの間)に養子になった経験を有する20代から50代までの男性250名及び女性250名”
を対象とした未成年者を養子とする普通養子縁組の実態に関する調査結果の一部です。
Q. 現在、あなたは、養親のことを「実の親」と同じように感じていますか。
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 養親を実の親と同じように感じている | 48.4% |
| そうではないと感じている | 32.2% |
| どちらともいえない | 19.4% |
このデータからも、約半数の人が「血縁がなくても家族として認識できる」と感じている ことが分かりますが、一方で3割以上の人は「そうではない」と考えており、家族の定義が一様ではないことが明らかです。
つまり、「血縁=家族」という価値観が一般的である一方で、「関係性で家族は成り立つ」という考え方にも一定の支持がある ということです。
再婚家庭の家族関係はなぜ難しいのか?
再婚家庭では、「家族とは何か?」という問いがより複雑になります。
- 夫が元妻との子どもとの関係を続けることに違和感を覚える
- 継子との距離感がわからず、どう接するべきかわからない
- 義理の兄弟姉妹との関係がぎこちなく、家族として接するべきなのか迷う
例えば先日、結婚5年目にして私の妻に、「○○さん(私のフィリピン人の継母)は、あなたのお義母さんなの? 一緒に住んでいたわけではないのに?」と言われました。
この発言を聞いたとき、私は思わずムッとしてしまいました。
なぜなら、私は妻に「母が2人、父が2人、妹が3人いる」と付き合い始めの頃から伝えていましたし、実際に会ってもいました。
にもかかわらず、5年経った今でも妻の中では「継母=母親とは思えない」という違和感があったのだと気づかされたのです。
私にとっては当たり前の「家族」でも、妻にとっては「血縁がないのに、なぜそんなに強く家族として認識するのか?」という疑問があったのかもしれません。
つまり、再婚家庭では、家族の定義が人によって異なるため、ズレが生じやすい のです。
血のつながりがなくても『家族』と呼べるのか?
これは、再婚家庭や養子縁組において多くの人が直面する疑問です。
家族の定義は一つではなく、関係性を築くことで絆を深めることもできます。しかし、それがすべての人にとって自然なこととは限りません。
私のケースでは、継母は私を「アナク(息子)」として、継母の家族(フィリピン在住の弟や妹)に紹介してくれました。継母の弟や妹も私を歓迎してくれとても嬉しかったことを覚えています。
フィリピン人の妹たちは「クーヤ(兄)」と呼んでくれることで、血のつながりを超えた家族関係を実感しています。実際、妹の学校行事に兄として参加したこともありました。
こうした「呼び方」だけでなく、日常の関わりやお互いの関係の築き方によって、家族としての絆が深まっていったと言えます。
しかし、すべての人が同じように感じるわけではなく、「血のつながりがないと家族としての絆を感じにくい」と考える人もいます。
養子縁組によって得られるもの:経済的支援 | 心理的な家族関係
先の調査結果での質問をさらに深堀したアンケートがありました。
「養親のことを具体的にどのような存在だと感じていますか?」 という問いに対し、257件の回答がありましたので、一部を抜粋しております。
養子縁組による関係性の実態
- 257件の回答のうち、約38%(97件)が「特になし」「わからない」など、明確な感情を持っていない。
- 「大切な存在」「自分の味方」「安心できる存在」 など、養親と強い信頼関係を築けたケースもある。
- 一方で「育ててもらったことには感謝しているが、父親とは思えない」「実の子との差異を感じていた」 など、経済的なサポートは受けたものの、心理的な親子関係は築けなかったケースもある。
- 「他人」「関わりたくない」「虐待の傷を残した存在」 という回答もあり、心理的な距離が全く縮まらなかったケースも存在する。
令和3年公益社団法人商事法務研究会による未成年者を養子とする普通養子縁組の実態に関する調査結果の概要
※他にも様々な回答結果がありましたので、読者の方も是非一度読んでみることをオススメ致します。
これらのデータを踏まえると、養子縁組によって「経済的な安定」や「生活の向上」は得られるケースが多いが、「心理的な親子関係」を築くことは容易ではない ことがわかります。
再婚家庭では、血のつながりよりも「どれだけ心の距離を縮められるか?」が重要 だと言えるでしょう。
家族としての役割と期待のズレ
「家族とは何か?」について考えるとき、多くの人は「家族としての役割」についても考えます。
家族の定義が「血縁」か「関係性」かという議論とは別に、「家族だからこそすべきこと」についての期待や考え方にズレが生じることがあります。
特に再婚家庭では、家族の役割に対する期待が異なるケースが多く、関係性のすり合わせが必要になります。
家族として求められる役割の違い
例えば以下のようなケース。
経済的援助に関する価値観の違い
- 「家族なのだから、経済的に困っているときは支えるべき」 と考える人もいれば、
- 「たとえ家族でも、本人が自立すべきであり、金銭的な援助は不要」 と考える人もいる。
特に、兄弟姉妹間や親子間での金銭的援助の必要性については、価値観の違いが大きく表れる。
親と子どもの距離感に関する違い
- 「家族なら、何でも相談し合い、頻繁に連絡を取るべき」と考える人もいれば、
- 「家族でも個々の生活を尊重し、距離を取る方がよい」と考える人もいる。
例えば、親が頻繁に「最近どうしてる?」と連絡をしてくるのに対し、子どもは「何かあったら連絡するから」と思っているケースがある。
どちらの価値観が正しいということはなく、こうした距離感の違いが、家族間のすれ違いを生むことがある。
育児や子どもへの関与の度合いの違い
- 「親として、子どもが成人しても積極的にサポートすべき」 という考えの人もいれば、
- 「子どもが成人したら自立すべきで、親の役割は終わる」 という考えの人もいる。
子どもが結婚した際、親がどこまで介入すべきかという点で意見が分かれることがある。
冠婚葬祭・行事への関わり方の違い
- 「家族ならば結婚式・法事・正月などの行事には必ず参加すべき」 という考えの人もいれば、
- 「家族でも個人の事情を優先し、参加は強制すべきではない」 という考えの人もいる。
再婚家庭では、こうしたイベントごとでの参加の基準が曖昧になりやすくトラブルの元となる場合もある。
介護や看取りの考え方の違い
兄弟姉妹間で、親の介護を誰が担うべきかについて意見が分かれることもよくある。
親が高齢になった際、
- 「子どもは親の介護をするべき」と考える人もいれば、
- 「親が子どもに頼るのは当然ではない」と考える人もいます。
また、再婚によってできた義理の兄弟姉妹との関係でも、「兄弟だから助け合うべき」と考える人と、「義理の関係なのでそこまで関与しなくてもいい」と考える人で意見が分かれることがあります。
このように「家族としての役割の認識の違い」は、日常生活の中でさまざまな場面で表れます。
「家族だから助けるべき」に違和感を感じる理由
再婚家庭に限らず、日本では「家族だから助けるのが当たり前」という価値観が根強くあります。
「親が困っていたら助けるべき」「兄弟姉妹は支え合うもの」など、家族に対する無条件の献身が求められることも少なくありません。
しかし、私はこの考え方に強い違和感を持っています。
「家族だから助ける」の前提がしっくりこない
冷徹な人間のように思われてしまうかもしれませんが私自身、
「家族だから助けることは当然」と言われると、「家族だからって、なぜそれが義務になるのか?」と疑問に思ってしまいます。
もちろん、家族が困っていたら助けたいという気持ちはあります。
しかし、それは「家族だから」ではなく、「自分が助けたいと思うから」です。
この違いは大きいと感じています。
「助けるべき」と「助けたい」の違い
「助けるべき」と「助けたい」は、一見似ているようですが、本質が異なります。
「助けるべき」 とは、血縁や家族関係を理由に、義務として支えなければならないという考え方です。しかし、この考え方に基づくと、たとえば毒親に苦しめられた人でも「家族だから」という理由だけで支援を強いられることになります。
一方、「助けたい」は、助ける側の意思に基づいた行動です。相手が家族であっても、自分が本当に助けたいと思えるかどうかを判断基準とすることで、納得のいく支援ができるようになります。
「家族だから助ける」という義務感ではなく、「助けたいから助ける」という意志のある行動が、より健康的な家族関係を築く鍵ではないでしょうか。
家族と自己犠牲の関係
家族のために自己を犠牲にすることが美徳とされることがあります。特に、日本社会では「親は子どものために尽くすべき」「子どもは親の面倒を見るべき」という価値観が根付いています。しかし、こうした考え方にはいくつかの課題が存在します。
1. 自己犠牲が生む負担
- 家族のために自分の人生を犠牲にすることが、結果として心身の負担を増大させることがある。
→ 親の介護をするためにキャリアを諦めるケースや、兄弟の借金を肩代わりすることで自身の生活が苦しくなるケースがある。 - 無理をしてまで家族に尽くした結果、精神的なストレスが積み重なり、家族関係が悪化することもある。
2. 助け合いのバランスが崩れる
- 一方的な自己犠牲が求められると、「助ける側」と「助けられる側」のバランスが崩れる。
- 「家族だから助けるのが当たり前」とされると、助ける側が疲弊し、助けられる側が依存する構図が生まれることがある。
- 親が子どもに経済的な援助を求め続けることで、子どもの将来設計が崩れることもある。
3. 家族と個人の境界線
- 家族であっても個人の人生があり、それぞれの価値観を尊重することが重要。
- 「家族だから助けるのが当然」という考え方は、個人の選択を制限し、自由な生き方を妨げる要因になることがある。
- 「親が決めた結婚相手と結婚すべき」「家業を継ぐのが当然」といったプレッシャーが、個人の意志を無視することにつながる。
助けることは義務ではなく、選択であるべき
家族の助け合いは一律ではない
家族を大切に思う気持ちは尊重されるべきですが、それが「犠牲」として強制されるべきではありません。家族同士の助け合いは、必ずしも義務や犠牲を伴うものではなく、それぞれの関係性によって多様な形があります。
「家族だから助けるべき」という固定観念ではなく、「助けたいから助ける」という意識が持てる関係性こそ、より良い家族の形ではないかと考えます。
お互いに無理なく支え合えることが、家族として健全な関係を築くための重要な要素です。
家族の中で自己犠牲を求めることが常識とされがちですが、それが必ずしも理想的な家族関係を築くわけではありません。助け合いのバランスを取りながら、それぞれの価値観を尊重し合うことが大切ではないでしょうか。
再婚家庭では「家族観のズレ」が生じやすい
このように、私は「家族だから助けるべき」という考え方に違和感を持っていますが、世間一般ではまだまだ「家族は無条件に助け合うもの」という価値観が強いです。
特に、再婚家庭ではこうした「家族観のズレ」が生じやすいと言えます。
例えば、
- 継親が継子をどこまで支えるのか?
- 実の兄弟姉妹と、義理の兄弟姉妹の関係はどうなるのか?
- パートナーの前の家族との関係はどこまで維持すべきなのか?
このような問題に直面したとき、「家族だから助けるべき」という価値観がぶつかると、違和感を覚えたり、無理をしたりすることになります。
再婚家庭においては特に、「家族だから助けるべき」ではなく、「助けたいから助ける」関係を築くことが重要なのかもしれません。
家族とは何か?再婚家庭における『新しい家族の形』
家族の形に正解はない
再婚家庭では、家族の定義が異なることで誤解や摩擦が生じやすい。
そのため、互いの価値観をすり合わせながら、無理のない関係を築くことが重要です。
家族のあり方は一つではなく、血縁の有無も関係なく、どのような関係を築くかが重要になります。
社会には様々な家族の形があり、それぞれの関係性の中で、自然に築かれる家族の絆こそが、本当の「家族」といえるのではないでしょうか。
ここまで、「血縁に縛られない家族の形」について話してきましたが、これは「血縁のある家族を否定する」ものではありません。
家族の在り方は人それぞれであり、血縁を重視する価値観もあれば、関係性を重視する価値観もある。
大切なのは、「どちらが正しいか?」ではなく、「自分にとって自然な家族の形は何か?」を見つけることだと思います。
私自身、妻の発言にムッとしたことで、「もしかして自分は継母や継父、妹たちを否定されるのが嫌で、家族だと言い張っているのか?」と考えたこともあります。
しかし、最終的には「私は関係性で家族が決まると信じているから、それを大切にしたい」と結論づけました。
このように、家族の定義は固定されたものではなく、自分自身で決めていくもの なのかもしれません。
再婚家庭では「家族の定義をすり合わせること」が大切
再婚家庭では、家族の形が一つではないからこそ、「家族とは何か?」をパートナーと共有することが重要になります。
例えば、
- 「前の配偶者との間にできた子どもとの関係をどうするか?」
- 「継父・継母と、実の親とのバランスをどう取るか?」
- 「義理の兄弟姉妹との距離感をどうするか?」
こうした問題に対して、「家族だから当然こうするべき」ではなく、お互いの価値観をすり合わせて、無理のない関係を築くことが大切 だと感じます。
まとめ:再婚家庭に必要なのは「家族のアップデート」
- 日本では「血縁を重視する家族観」が根強いが、再婚家庭では「関係性で家族を築く」ケースも多い。
- 家族の定義は人それぞれであり、価値観のズレが生じやすい。
- 「家族だから〇〇すべき」ではなく、「助けたいから助ける」関係を築くことが大切。
- 再婚家庭では、「家族とは何か?」をパートナーとすり合わせながら、新しい形を模索することが求められる。
家族の形に正解はありません。
再婚家庭では、従来の「血縁=家族」という価値観にとらわれず、「自分たちにとって自然な家族の形」を見つけること が、より良い関係を築く鍵となるのではないでしょうか。
ここまで記事を読んでいただきありがとうございます。
家族の問題はデリケートで、身近な人にはなかなか相談しにくいものです。
そんなとき、第三者の専門家に話すことで、気持ちが整理され、解決策が見えてくることもあります。
無料相談を実施しているカウンセリングサービスもあるので、「話を聞いてもらうだけでも…」という気持ちで試してみてはいかがでしょうか?
参考文献